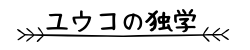今回は色彩検定は実用的であるか?というところをお話したいと思います。
私もこの資格を取得して、同じ資格を持っている方と何人かお会いしました。皆さんどんな職業に就いているのか、そして私が経験した資格の活かし方も紹介します。
色彩検定と言っても資格制度は3種類ある
基本的な学ぶ範囲は同じなのですが、色彩検定には3種類の団体の検定があります。
それぞれの特徴を見てみましょう。
A・F・T色彩検定
最も受験者数の多い検定試験ですね。私もこちらの検定を受けました。
主催団体は「公益社団法人色彩検定協会」となります。時期になると電車内の広告でもたまに見かけることがあります。
こちらの団体の検定試験は、主にファッションの要素が大きく、試験内容にはファッションの歴史や主要なテキスタイル(洋服の柄のことです)の単元も出てきます。
他にも、お部屋の空間コーディネートなどの問題もありましたね。
試験日は1年のうち6月と11月。
6月の試験では2級と3級、11月試験では1級、2級、3級の試験が受けられます。
1級試験は2次試験(実技)があり、12月上旬に行われます。
東商「カラーコーディネーター試験」
簿記試験や福祉分野などの東京商工会議所が主催する検定となります。こちらも知名度が高いですね。
試験内容の特徴は色彩の理論や体系などがあり、主に工業系の商品開発などに役立つ内容のようです。
こちらは今年度までは1級~3級という区分で検定試験があったのですが、2020年からは「スタンダードクラス」「アドバンスクラス」と名称が変わり、試験月はどちらも6月、11月となっています。
色彩士(カラーマスター)検定
こちらの検定は「全国美術デザイン教育振興会」(略称ADECアデック)が主催する検定試験となります。
デザイナー、アーティスト向けの試験内容となっており、美術の要素が大きいところがこの試験内容の特徴です。
こちらは1級~3級まであり、1級に関しては2級試験を合格しないと受けられなくなっており、1級試験にはプレゼンテーション作成など本格的な試験内容があります。
試験日は1月と9月にあります。
こちらの講座では、上記検定「A・F・T色彩検定」「東商カラーコーディネーター試験」の2級・3級対策が行えます。
聞き取りやすい講師の授業やスマートフォンにも対応しているので、スキマ時間も有効活用できます。
今回はA・F・T色彩検定についての活躍例を紹介します。
活かせるか活かせないかは自分次第

色彩検定の資格を活かせるか、活かせないかはまずは自分が就職先でどのようにしたいか、ということから始まると思います。
2級、3級試験は主に学生の就職活動のために、大学生が受験することが多いです。(私もこの試験は学生の頃受験しました。)
また就職のためにこの資格を取るというわけではなく、あくまで自分のセンスアップのため、自分を変えるために試験を受けられる方もいます。
実際にこの資格を取得しその後色彩心理について学んだ主婦の方は、色彩心理の授業を受けるにつれだんだんと服装が明るくなり、またカリキュラムが終わるころには明るい性格になりましたね。
最初は暗い色の洋服ばかり着ていた方だったのですが、授業を重ねるにつれ、段々と明るい色を着るようになり、他の生徒さんとも話しかけてる姿を見かけることができました。私もその方と何度かお話しました。
また日ごろの細かい1部分でも色彩の知識を活かすことができます。
私はアルバイト先のレストランで統一感をだすお店のコーディネートを任されたこともありますし、家庭での毎日の食事でもおいしそうに見える盛り付け方などを考える機会を持つことができました。
友人や家族から洋服のコーディネートについて相談されることもしばしばあります。
2級、3級を就職に活かすには
2級、3級は大学生や専門学校生の方が、就職のために受験する方が多いですね。
学ぶ範囲が幅広いので、それだけ狙える就職先が広いということになります。
公式ホームページには、「活かせるお仕事」として、アパレル販売、ファッションコーディネーター、ネイリスト、美容師、メイクアップアーティスト、広告・出版産業の企画広報、印刷業、WEBデザイナー、インテリアデザイナー、建築デザイナー、建設業、プロダクトデザイナー、塗装業、景観担当者、パティシエ、テーブルコーディネーター、営業、フラワーデザイナー、ウエディングプランナーとあります。
「色彩検定は役に立たない」という人の勘違い
もちろんこの資格、「役に立たない」と噂する人も多くいます。
しかしそれは併用する仕事を持っていないこと、それと学生の方が就職時にこの資格を利用した自分の取り柄やセールスポイントを伝えきれていなかっただけで、履歴書に資格名を書いただけで終わっていたのかも知れません。
履歴書に資格名を書いただけでも、面接担当者がその資格の内容をよく知らなければ意味がありませんからね。
社会人が色彩検定を取得するなら

実績も就職もしていない、それでも色彩検定を受けてみたいという社会人の方なら、1級まで取ることをおすすめします。
見事1級に合格できたら、学校やカルチャースクールでこの検定の対策講座を開くことのできる「色彩講師」の研修を受講する事ができるからです。
1級に合格後、5年間はその研修の案内状が届きます。5年後以降でも研修を受けることは可能ですが、募集期間などがあるのでその都度公式ホームページのチェックが必要ですね。
また、パーソナルカラー診断の講習を受け、パーソナルカラーアナリストとして活躍する方法もあります。
このパーソナルカラーアナリストという職業は自分でお店を持たれている方もおりますが、百貨店やスーパーのイベントでも見かけることもありますし、複数のパーソナルカラーアナリストが登録し活躍されている団体もあります。
また私の知り合いではカラーセラピストとして活躍されている方もおりましたね。
こちらも公式団体の講習を受け、道具を揃えお店を持つことができます。
まとめ
色彩検定を取得した後のたくさんの活かし方を紹介しました。
かく言う私は以前の就職先では化粧品開発のファンデーションカラーの測定もしました。
このようにWEBの制作になどでも活用していますね。
参考:公益社団法人 色彩検定協会
参考:東京商工会議所
参考:全国美術デザイン教育振興会
参考:株式会社トゥルーカラーズ