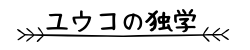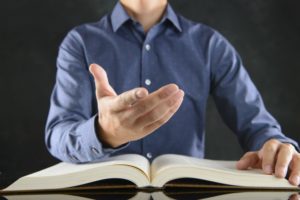今回は年金アドバイザー試験について調べてみようと思います。
あまり知名度のない資格ですね。就職活動には有利なのでしょうか?
年金アドバイザー3級はこんな試験

この試験を行っている団体は、「銀行業務検定協会」というところが行っています。
その目的は、銀行などの金融機関での窓口業務、渉外業務を行う時に年金について説明したり、年金の知識を問われたりするときに活躍するそうです。
将来、何歳になったら年金がもらえるのか、その額はどれくらい?など、年金の不安は年を重ねるにつれ心配になってきますよね?
国民年金法、厚生年金法は改正や経過措置などが度々行われていて、年々複雑になっていき、その仕組みはサッパリ分からないという方も多いのでは?
銀行員の方の受験が多いのかと思われますが、3級に関しては、社労士(社会保険労務士)試験を受けられる方、もしくは受けた方も受験します。内容や範囲が近いそうです。
また、3級があるのですから、もちろん難易度に合わせて他の級もあります。年金アドバイザーについては4級、3級、2級と3種類あり、1級は存在しません。
その難しさをまとめてみると、
- 4級…窓口対応について、年金について最も基礎的な知識を問う。
- 3級…やや難しく、顧客からの年金相談を行えるための基礎知識と応用力を問う。
- 2級…年金保険の専門家として、顧客からの相談のほか、企業研修などの講師も行う。筆記試験や計算問題もあり。
となります。
どんな人が受験する?
金融機関にお勤めの方を対象にした試験なので、3級までは金融機関にお勤めの若い方が6割ほどいらっしゃるそうです。
また、先ほども紹介した通り、社労士やFPの受験者、自己啓発のために受験する方もいらっしゃいます。
国家資格ではないので、この資格を取得してもすぐにその専門的な仕事に就くことができるわけではないですが、一般的な企業でも総務課などに配属し、年金を受けながら会社に在籍している、在職老齢年金の従業員の人に説明や相談に乗るなど、応用することができます。
受験者数、合格率は?
年金アドバイザーの試験は2級、4級が年に1回(3月)、3級が年に2回(3月、10月)行われます。
1回の受験者数は毎回2級、4級が2,000人程度、3級だと約10,000人が受験されます。
やはり3級が基準といった感じですね。
各回、級ごとの受験者数、合格率は以下の通りです。
| 級数 実施年月 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
| 4級 2018年3月実施 | 1,540 | 907 | 60 |
| 3級 2018年10月実施 | 7,425 | 2,644 | 35 |
| 2級 2018年3月実施 | 1,638 | 432 | 26 |
私としては大体平均して、半数以上の合格者が出ていると難易度は易しくなると考えますので、半数以上の合格者が出ている4級はそれほど難しくはない、といった感じです。
やはりこの試験は3級がベースとなっていくようです。
社労士試験との範囲はどのように違う?

社労士受験の方が力試しとして受ける年金アドバイザー3級は、どういった範囲が出てくるのでしょうか?
こちらの試験は具体的な年金の範囲が多いので、内容も細かくなることが多く、社労士試験では一般常識での範囲のものが問われることもあるそうです。
例えば、
- 合計特殊出生率
- 高齢化年齢の比率
こちらについては統計として社労士試験でも押さえておくポイントとなっていきますが、
- 社会保障給付費
- 年金積立金の額
- 公的年金の加入者数
- 平均寿命
など、具体的な全体額の合計も問われるそうです。
ここは、毎年数値が変わっていく箇所なので、受ける試験が何年何月何日を基準にしているかなどもチェックが必要です。
沿革についても問われますが、こちらも健康保険法などほかの法律と混ざらないようにしたいですね。
また、年金請求書の送付、税金などに関係する掛金の控除の問題もあるそうです。
年金アドバイザー専用の通信講座を出しているところは少ないのですが、こちらの講座なら安心して取り組むことができます。
独学で学習するには?
年金アドバイザー3級の問題は、過去問から出題されることがほとんどなので、過去問題集の繰り返しが効果的です。
とはいえ、統計や改正点は年々変わっていくので、間違った数値を覚えないようにすることも大事ですね。
まとめ
年金アドバイザー資格は仕事にすぐに直結するわけではありませんが、役に立たないわけではないと思います。
高得点で合格するとメダルがもらえるので、モチベーションも上がりますよね。