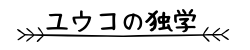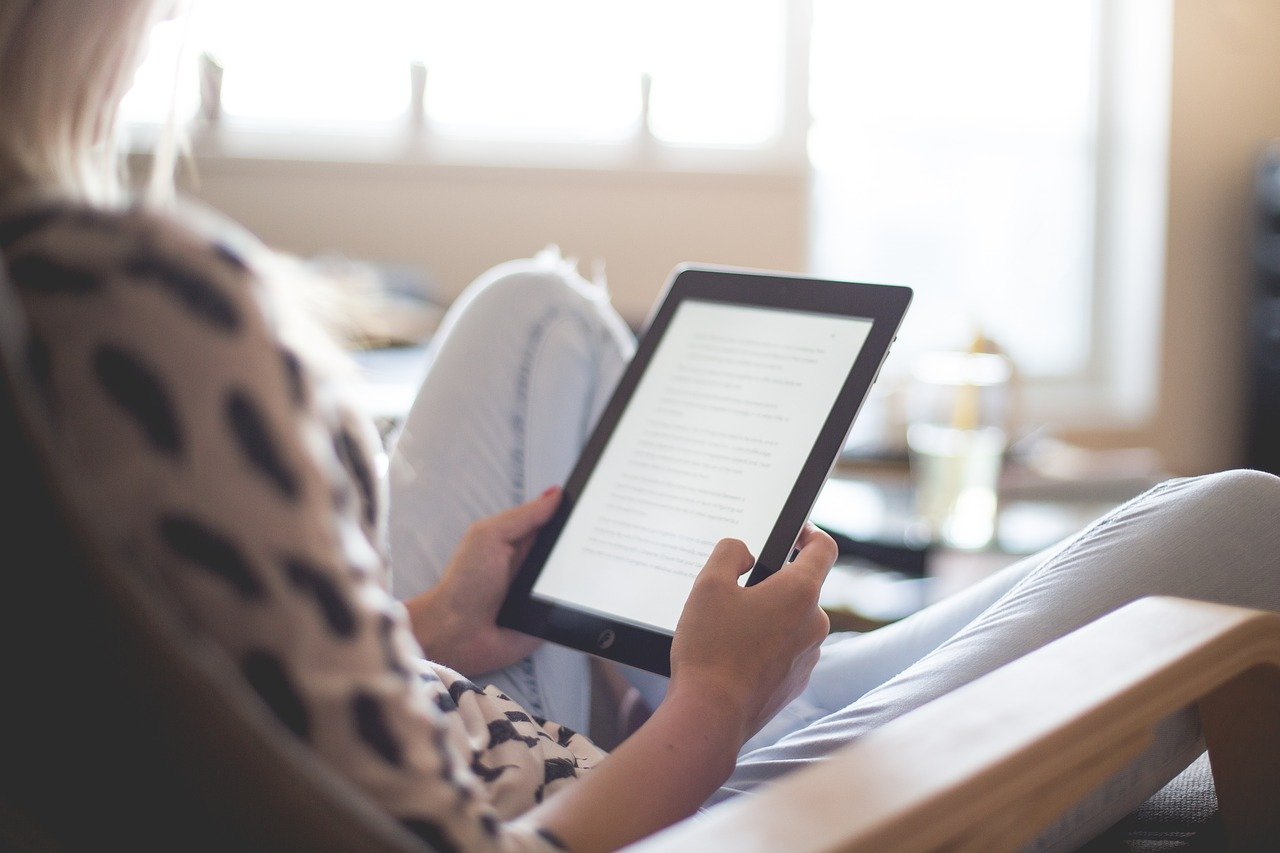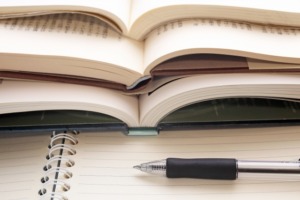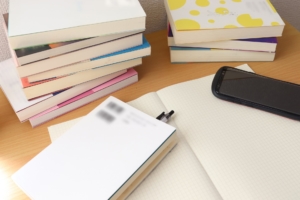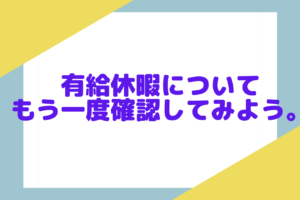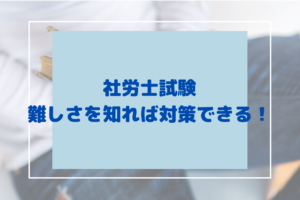4月を過ぎると、物の値段の改定など生活のいろいろな箇所で改定が行われますね。
会社の社会保険事務ももちろんそう。雇用保険のことや社員の入社、退職に合わせて変更された事務手続で私も日々あわただしく過ごしています。
社労士試験を受験する方にとっては、この時期から法改正や白書対策に手を付ける方が多いと思われます。
そこで、今回は独学で勉強されている方におすすめの法改正・白書対策勉強法を紹介していきたいと思います。
社労士試験の法改正・白書対策は必須項目
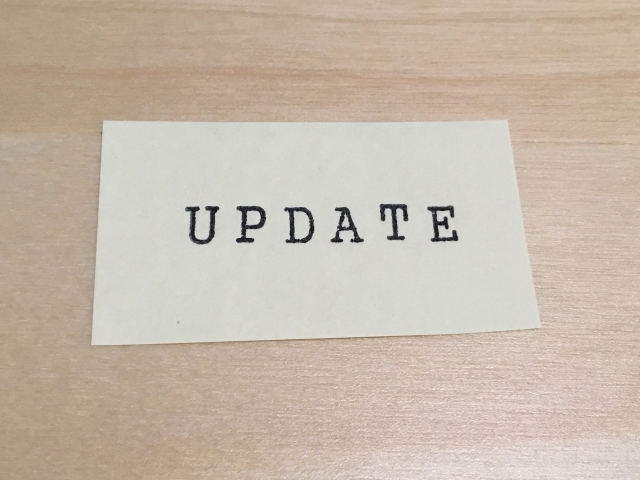
2020年度試験の受験案内が、4月10日(金)より配布されるそうです。
それによると試験日は2020年8月23日(日)、合格発表と試験の解答は2020年11月6日(金)となっています。
例年と比べて合格発表が早くなった気もしますが、受験後から合格発表までの過ごし方は、ただぼーっと過ごす方、自己採点を早く終わらせて次のステップに進む方、いろいろですね。
駆け込みで試験に挑戦する方に向けての記事はこちらから

試験問題の法改正内容はこの日まで
さて、実際の試験で行われる法律の内容は、毎年この受験案内の配布日に合わせているようです。
つまり2020年度の試験問題に出る内容は、2020年4月10日現在施行されているものとなるんですよね。
駆け込みで集中して勉強を始める方はいいとして、社労士試験の勉強は半年以上かけることが多いので、勉強開始時に購入したテキストでは、改正内容が書かれていません。
また試験科目の中の、「労務管理その他の労働に関する一般常識」「社会保険に関する一般常識」は、直近で発表された厚生労働白書や労働経済白書、統計データから出題されます。
この白書の冊子、官報を取り扱っている書店で買うことができてたまにレジ前の本棚に並んでいるのですが、大体300ページくらいの厚さでしたね。大きさはA4でした。
給与額の平均や雇用の動向などの数字を覚えていくのですが、どうしてこれらを覚えていかなくてはならないのかというと、時代の変化に柔軟に対応するようにということなんですよね。
というわけで法改正対策、白書対策の勉強を始める時期はこれからという方が多いのですが、独学で勉強されている方にとっては情報をどれだけ効率的に集めなくてはならないかというところがカギとなります。
そこで、対策方法5選をおすすめ度の高い順から紹介していきたいと思います。
独学者向けの法改正対策5選。おすすめ度の高い順から紹介します。

法改正、白書の対策方法を5段階で紹介していきます。
その1.オプション講座を受講する。(おすすめ度★★★★★)
この時期になると、勉強開始時に取り組んだ法律の復習をしつつ、過去問やまとめ問題の繰り返し量も多くなっていきます。
その中でまた新しい範囲を勉強するとなると、なるべく調べる手間を省きたいですよね。
そこで、ここは通信講座のオプションを使ってみましょう。
各資格学校では直前対策講座を用意していますが、入会手数料を払わなくてもよい通信講座を選ぶといいですね。
いくつかある直前対策講座をセットで購入するとお得になります。
その2.直前対策本を購入する(おすすめ度★★★★)
法改正のための対策本は、テキストより遅れて発売されます。
対策本を利用すると膨大な法改正、白書の内容をコンパクトにまとめているので、絶対に外せない内容を確認することができます。
私のおすすめは、資格の学校であるTACから出版されている、「無敵の社労士 完全無欠の直前対策」です。
発売日が5月以降となっていますが、こちらの「無敵の社労士」シリーズは年度ごとに4回発行されていて、巻末にある暗記カードは通勤時によく利用していました。
この前に発行された「無敵の社労士2」についても、独学者の方が分かりにくい要点や予想問題もついているので全4冊持っていても無駄にはなりません。
ただ、表紙が派手なので通勤時に読むときはカバーを作ったほうがいいかなと思います。
その3.対策動画を観てモチベーションアップ(おすすめ度★★★)
法改正対策の解説動画を観ることもおすすめです。
ただ、上記の2つと比べるとアウトプットとしてそれにあった問題を解くことができないので、その点は他の問題集とすり合わせて解くしかないですよね。
こちらの講座は入門編からの動画を購入することなく、支払いが月額払いなので必要な所だけを学習することができます。
また、他の資格の動画も観ることができるので、合わせて取っておいたほうがいい資格なども勉強できます。
その4.社労士雑誌を購入する(おすすめ度★★)
新しい法改正内容を常に入手することもできますし、モチベーションの維持にも役立ちます。
本試験会場でこの雑誌を読んでいる方、数人見かけましたね。
その都度新しい内容が発売されますが、1年間購入すると1~2万円ほどになります。
その5.人事労務マガジンを購読する(おすすめ度★)
直接厚生労働省のメルマガ登録をします。
社会保険関連の情報は届きにくいですが、一般常識対策にもなり、また直接厚生労働省発行の法改正となったお知らせなどを観ることができます。
ただ、このお知らせやパンフレットは一般の人にも分かりやすく作成されているので試験内容としては少し情報量が少ないかもしれません。
バックナンバー(過去に配信された内容)も観ることができます。
絶対やってはいけない法改正対策とは?
やってはいけない勉強法は、法改正の内容をインターネットで収集するということです。
まずネットで検索する手間がありますし、その内容が正しいかどうかは分かりにくいものです。
また自分でどのくらいの量を知ったほうがいいのかは判断が難しいし、問題を解くこともないので頭に入りにくいんですよね。
まとめ
今回は法改正や白書の対策方法を私の経験も踏まえてまとめてみました。
自力で情報を集めようとすると、貴重な勉強時間を削ることになりますし、どこまで覚えたほうがいいのか分からず、他の教科の勉強がおろそかになるということですね。
試験日まで残りわずかですが、このまとめがお役に立てたら幸いです。