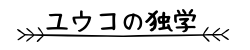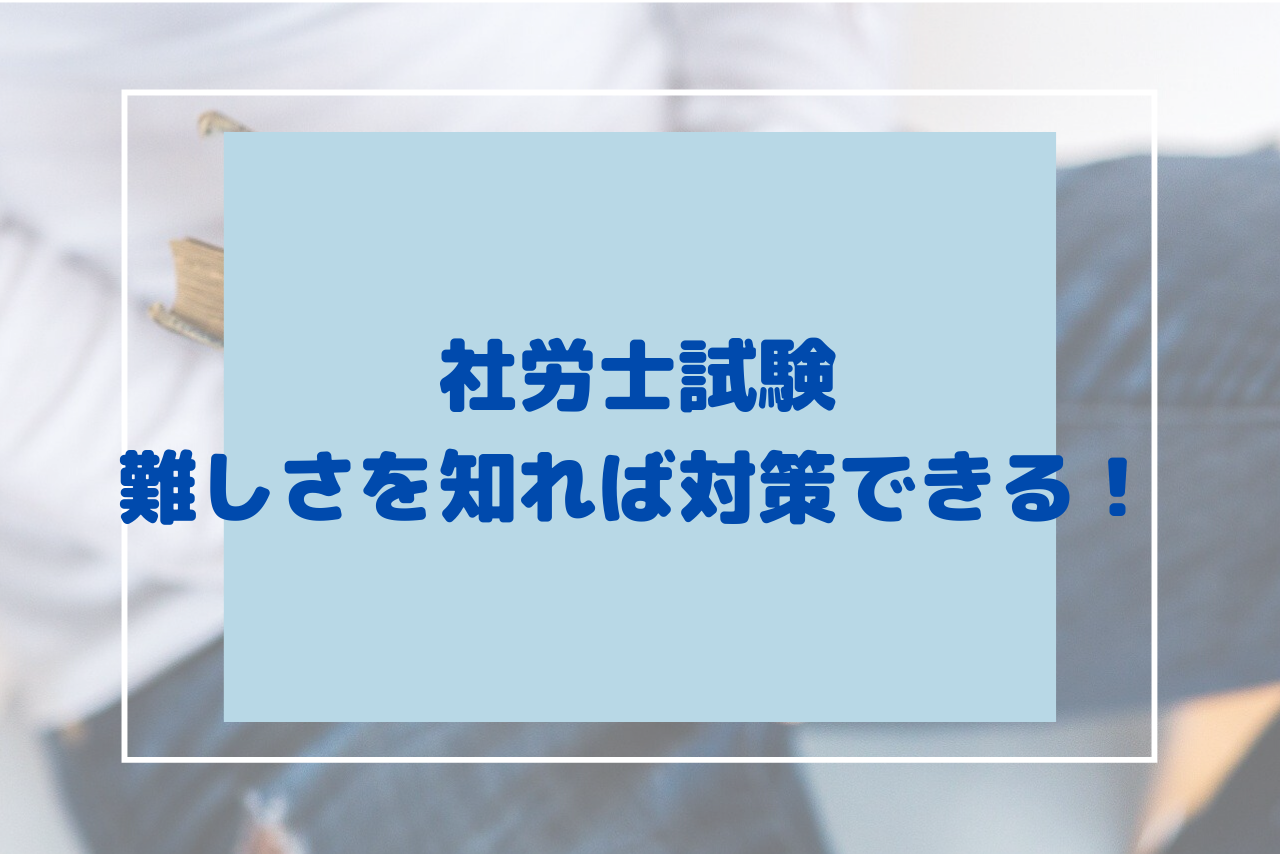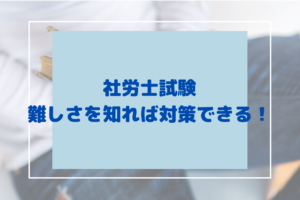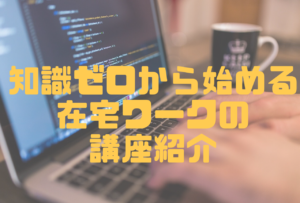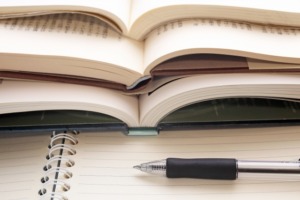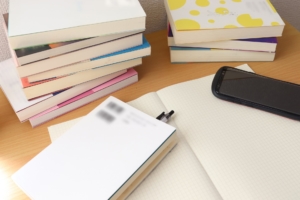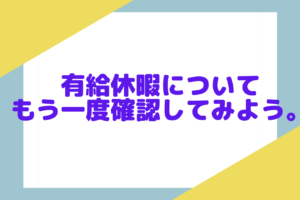今回は社会保険労務士「社労士」試験の難易度を徹底調査していきます。
年々合格率が低くなっている社労士試験。合格率が低くなるとやはりその年の難易度は高いと思いがちですが、難しさを分析していけばどのように勉強していけばいいのかが分かると思います。
模擬試験で合格ラインに乗った私が、その難しさを詳しく解説します!
合格率と難易度の関係
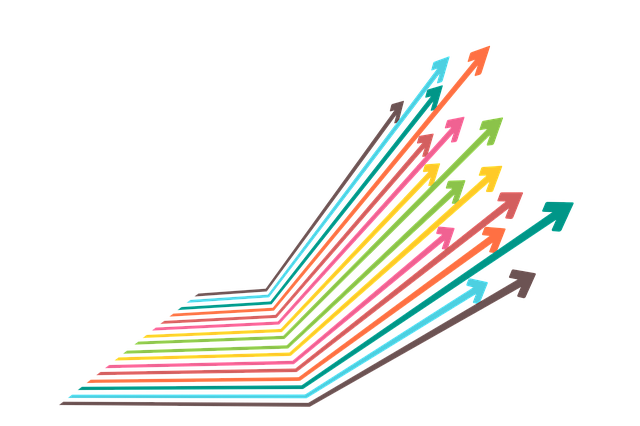
社労士は、昭和43年に社労士法(社会保険労務士法)で制定された国家資格です。
この資格を取るとどのような仕事ができるのかと言うと、労働者が会社の入社から退職までにかかる社会保険などの手続きや労働問題などにもかかわる専門家となります。
就職先としては、社労士事務所や労働保険事務組合、企業内の総務や法務の専門家として活躍することもできます。
詳しい業務内容は以下の通りです。
- 雇用保険や社会保険、労災保険の加入・脱退・給付の申請書作成や届け出を代行する。
- 労働者名簿の作成や賃金台帳などの帳簿を作成する。
- 就業規則作成や届け出、36協定などの労使協議の届け出。
- 労働者の採用や社会保険、補助金申請、労働安全衛生、社員教育等の相談や指導を行う。
- 労働関係のトラブル相談等…
試験に合格し、かつ、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令に定める事務に従事した期間が通算して2年以上あると晴れて上記の仕事をすることができるというわけです。
またこの実務経験がなくても、合格後、講習を受けることで社労士として登録することができます。
試験日は毎年8月の第4日曜日(2020年度は5月上旬現在、試験日程に変更はないですが今後アナウンスがあるかもしれません。)です。
というのは、2020年度春に予定されている資格試験は中止が相次いでいるからです。

試験内容はこちらでも詳しく書いています。

毎年5月末までの願書提出ですが、添付する卒業証明書などは提出期限が延長となっています。
直近の合格率は?
最近の合格率を見てみると以下の通りとなります。
| 年度 | 合格率(%) |
| 平成22年 | 8.6 |
| 平成23年 | 7.2 |
| 平成24年 | 7.0 |
| 平成25年 | 5.4 |
| 平成26年 | 9.3 |
| 平成27年 | 2.6 |
| 平成28年 | 4.4 |
| 平成29年 | 6.8 |
| 平成30年 | 6.3 |
| 令和元年 | 6.6 |
全体的に10%を切る合格率ですね。
平成27年度は3%を切る合格率となっているのですが、実は私はこの年に初めて試験を受けていました。
最初の試験ということでその難しさも感じることもできなかったのですが、何年か受けてみて、この年は難しかったという差は感じませんでした。
というのは、毎年難しさによって救済措置などもあり、各法令ごとに合格点が設けられ、かつ、全体の合格点ラインが決められているんですね。
他の資格試験では法令ごとに合格すると、その法令は来年に持ち越されることもあると聞きましたが、社労士試験では全体の合格ラインもあるので持ち越されることはありません。
ただ、どんなに合格率が低い年があっても、資格学校の解説動画の先生方は「基本を押さえていればできていたと思います。」というんですよね。
独学で勉強をしている方でも、模擬試験は最低3回は受験しましょう。模擬試験を受験すると、特典として予想問題集がプレゼントされたり、本試験後の回答解説や動画を観ることができます。
確かにテキストや授業の基本の法令を覚えていれば解けるのですが、ただ字面を覚えるわけではなく、一つ一つの法令について深く考え、問題集を解くことで理解を深めておくことが日々の勉強の中で大事なんです。
もちろんくり返し問題を解く勉強スタイルは誰しもやっているのですが、繰り返し問題を解くにはコツがあります。

問題を解く練習は最初はかなり時間がかかりました。解く度にテキストを見返す作業となっていきますからね。
また、回答にある補足説明も大事。場合によっては他の法令との違いを比べた覚えやすい表が書かれてあることもありますし、条文に関するほかの事例が本試験や模試に出てくることもあります。
難易度を理解したうえで気を付けておくべきこと3つ

本試験を受ける前の勉強の仕方として、次の3つを意識して勉強すると点数も上がります。
実務経験が逆に難易度を高めてしまう原因
実際に社員の標準報酬を決定する算定基礎届を提出したり、労働保険料を計算している仕事をしている方は自分の実務経験を過信してしまって無意識に勉強がおろそかになってしまう危険があります。
実務と法律は別です。実務で得た知識の感覚で問題を解くと不正解になります。
この原因は自分の法律の理解が間違っていたということなんですね。
ただ正しい法律の理解を深めれば実務と結びつきますので、まずは貪欲に学ぶ姿勢をつけましょう。
例えば実務では細かい徴収法の範囲である労働保険料は、パソコン上では報酬額や年齢を入力するだけで年度更新の申告書ができてしまいます。
しかし実際の試験では、その計算方法を理解して自分でひっ算を立てて計算しなければなりません。
試験時間が限られている中で、素早く計算する力も求められているということなのです。
また、国民年金法の問題ではその人の年齢から受けられる年金制度を答える問題もあり、年数計算も必要になってくる場合もあります。
年齢計算、日数計算を簡単にする方法をまとめた記事はこちらから
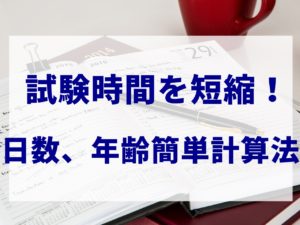
社労士法制定は昭和43年。その処理は紙ベースの申請書のやり取りなので、その時代背景に合わせた法律がつくられているのです。
長丁場の体力勝負
本試験のスケジュールを見てみると、他の資格試験と比べてダントツに長いんですよね。
午前中 10:30~11:50(80分) 選択式:8科目:40点満点
https://www.sharosi-siken.or.jp/exam/howto.html
午 後 13:20~16:50(210分) 択一式:7科目:70点満点
時間だけは長く余裕かなと思っていてもそうではないところが特徴。特に択一式の問題は70問あり、1問につき3分で解かなくてはなりません。
5択の選択肢も文章が長く、その中で正誤を判断します。
解き方として自信をもって正しいものを選ぶときはその分時間を短縮することができますが、その自信度を高めるためにはやはり日ごろの練習が必要となってくるのです。
また、実際に本試験を受ける会場は大学の講堂などがほとんどなのですが、イスが固く腰が痛くなる方もいらっしゃいます。
以前には座布団の持ち込みもOKだったのですが、最近では禁止となっています。
勉強期間も長いと継続する力が必要
本試験の勉強時間は平均して1000時間と言われています。

この長い勉強時間を確保するためには、日ごろの生活に合わせた計画を立てます。
短期間で合格する方はその分1日の勉強時間が長いので、初学者の方はあまり短期間で合格された方の体験談を過信しないほうがいいですね。
だんだんと量が多くなっていく問題を繰り返し、かつ解説を細部まで理解する作業に、短時間で効率よくこなす方法はありません。
なので1年がかりの継続力が必要となっていくわけです。
計画の立て方としては、私は1週間で自分の立てたタスクをこなしていくという方法をとりました。
まとめ
社労士試験に関しては、早いうちに難易度の高さの原因を知っておくと、これから勉強する方にとってはイメージが付きやすいと思います。
ただやみくもに勉強するだけではうまくいかないので、以上の点を意識して勉強してみましょう。