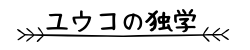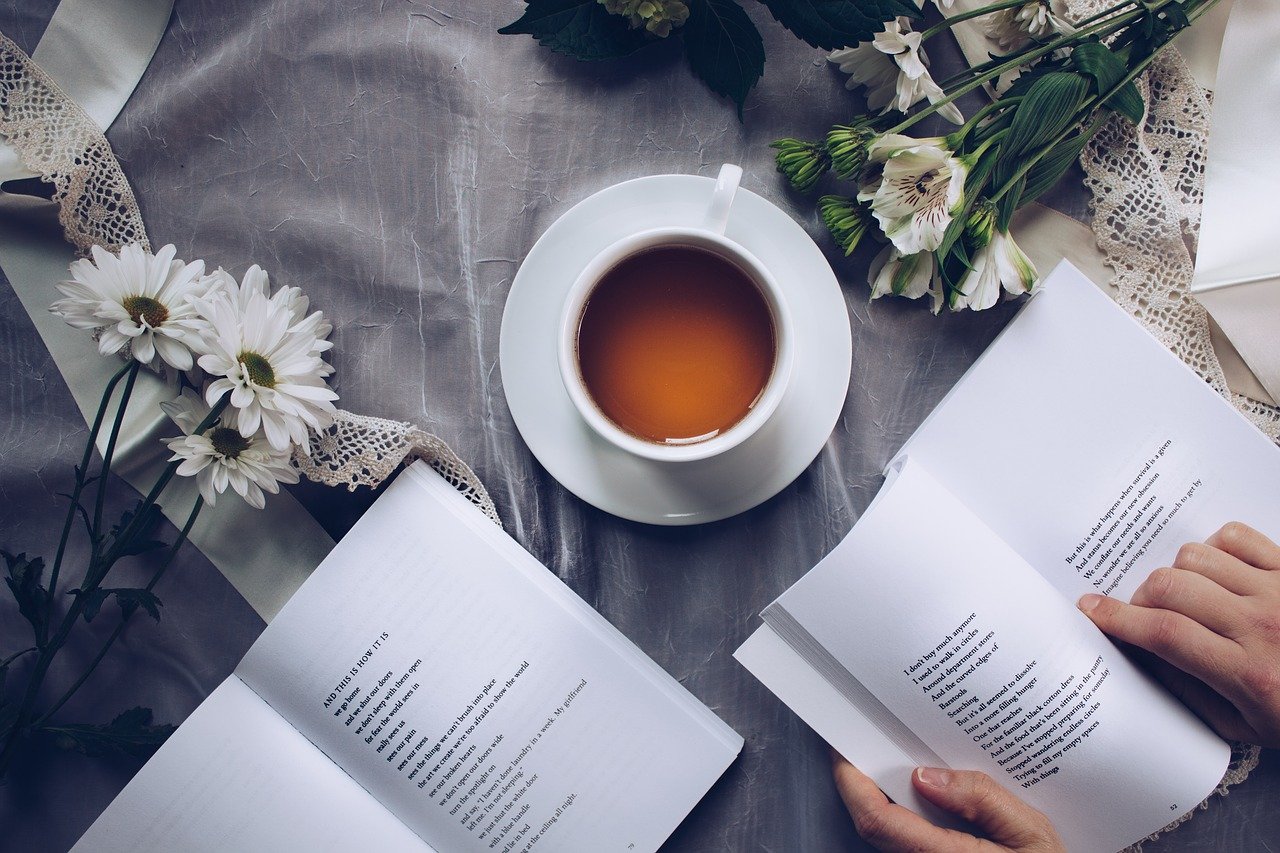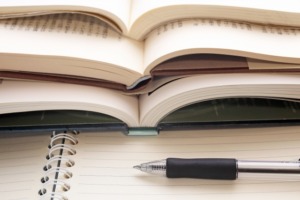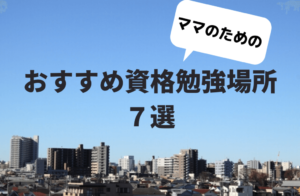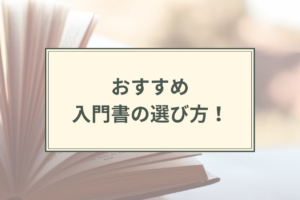今回は人気の資格試験に合格するための勉強時間と合格率をまとめました。
とはいえ一番最初に言いますが、これはあくまでも目安として使っていただきたいです。
初学者にありがちな失敗として、勉強時間を把握してその時間勉強すれば合格できると思い込んでしまうというものがありますよね。
このトータルの時間に安心するのではなく、必要な勉強時間を知ったうえで自分の生活の中でどのように勉強時間を確保していくかが重要だと思います。
主な資格の勉強時間と今年の試験日程などを発表!
世間的に言われている資格の勉強時間、2020年の試験日程や合格率をまとめました。
| 勉強時間 | 試験開催日時(2020年) | 合格率(2019年) | |
|---|---|---|---|
| 宅地建物取引士(宅建) | 400時間 | 10月18日 | 17% |
| 社会保険労務士 | 1000時間 | 8月23日 | 6.6% |
| 行政書士 | 1000時間 | 11月8日 | 12.7% |
| 中小企業診断士 | 1000時間 | 1次 7月中旬 2次 10月中旬 | 30.2% |
| ファイナンシャルプランナー2級 | 150~300時間 | 5月24日、9月13日、21年1月24日 | 43% |
| ファイナンシャルプランナー3級 | 80~150時間 | 5月24日、9月13日、21年1月24日 | 78% |
| 簿記2級 | 100時間 | 6月14日、11月15日、21年2月28日 | 12~27% |
| 簿記3級 | 50時間 | 6月14日、11月15日、21年2月28日 | 43~56% |
試験日程についてはまだ確定していないものもありますが、それぞれ申込日時が2~3か月前にあることが特徴なので、それぞれの公式ホームページを見ることをおすすめします。
ざっと表にまとめてみると、やはり合格率が低いものほど必要な勉強時間が多いことが分かります。
1000時間のものは年に1回試験が行われているものが多いので、必要な勉強時間も1年がかりということですね。
毎日3時間勉強することで大体1年かかることになるでしょう。
紹介した資格について、おすすめの通信講座を比較しました。こちらから読むことができます。
資格別勉強時間のポイントは?

それぞれの資格の勉強時間についてポイントを説明していきます。
宅地建物取引士(宅建)
こちらの資格については過去にも比較や勉強方法を紹介したのですが、当然、大学で法学部を専攻している人や不動産の業界で働いている人は勉強時間を短縮できると考えられます。
しかし、自分の仕事で携わっている範囲を軽めに勉強することは良くないと考えます。あらゆるケースの中の一部分にすぎないので、細かい論点をチェックすることは怠らないようにしたいものです。
関連記事はこちらからどうぞ。


社会保険労務士
社会保険労務士は、企業の労務人事、保険などの専門家となり、指導や書類の手続きなどを行う仕事となります。
というわけで、企業の総務人事の方が有利に勉強できそうですが実はそうでもなく、書類の書き方などよりもその制度をどのように説明していくかが問題として出てくるので、強化により免除制度が効かない場合は全部の内容を勉強しなければなりません。
働きながらなら、1年を要します。8月下旬に試験となるので、前年の9月から勉強を開始することがベストです。
行政書士
行政書士は法律専門の国家資格ですが、受験資格に年齢や学歴を問われないので誰でも挑戦できる資格です。
勉強する内容も幅広く、業として取り扱える書類も多くなってくるのでそれだけ必要な勉強時間も多くなってくるところが特徴です。
中小企業診断士
経営コンサルタントとして唯一の国家資格となる中小企業診断士は、学ぶ範囲も広く勉強時間も長い時間を要します。
また、1次試験、2次試験もあるのでそれぞれに対応した対策も必要ですよね。
ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナーはお客様のお金に関するアドバイスをする仕事となるので、こちらも幅広い知識が必要です。
とはいえ3級のは6割できれば合格となり、2級のほうは実技試験もあるので対応した勉強が必要です。
簿記2級、3級
上級になるほど大きな企業に対応した会計の知識が必要とされます。
過去にも関連した記事があるので、こちらもお読みください。


大切なのは量より質。それを実現させるための工夫とは

全体的な勉強時間を把握すると、最初に計画を立てるときにとても参考になると思います。
しかし、勉強の仕方にも注意が必要です。
1日の時間を決めてその時間帯に内容をこなすよりも、直前期になれば短い時間帯で繰り返す方が頭に入りやすいと言われています。
計画の立て方や過去問題の勉強法もまとめました。



まとめ
勉強を始めるときにその合格率や概要を知っておくことはとても重要です。
テキストを手に入れるときに、最初の導入部分を飛ばしてしまうのはもったいないことです。
是非こちらの勉強時間を把握して、対策してみてください。