資格の勉強にはまず、テキストの読み込み&講義動画の視聴が王道となりますね。
しかし、単元ごとの問題は解けるのに、予想問題、過去問題が解けない、分からないということはありませんか?
計画的に勉強したのに、もう一度テキストや動画を最初から…となると、試験日までに間に合わなくなりますよね。
特に試験直前期間には、模擬試験の解きなおし、過去問のくり返しなどに時間を取られて、体系的に勉強が進んでいるのか、自分は本当に覚えられているのか気になるところです。
今回は、
- テキストの読み込みをしたのに、予想問題が解けない。
- 計画的に勉強しているのに、覚えているのか不安だ。
- 資格学校、通信講座の模擬試験でなかなか点数が伸びない。
という方のために、予想問題の活用のしかたを分析してみました。
ざっくりとした把握になっていないか
テキストの中の重要な語句、また、講義などで注目されている論点はしっかりと覚えていても、いざ問題を解いてみると、解けないということがよくあります。
試験問題が択一式になっている資格などは、微妙な違いで○×の判断をすることもしばしば。
例えば、「~以上」、「~未満」、「知りえた日から○日以内」、「通知した日の翌日から○日」などの細かい箇所ですね。
暗記カードや暗記用アプリでは数字や重要語句は覚えられても、このような細かい箇所は問題全体や、答えに書かれている解説まで読まないと、気づかないことが多くあります。
何回も正解している問題でも、解説文に見落としやすい論点が書かれていることもよくあります。
ポイントはノート等に整理して、見直したいですね!
社労士試験で私も良く活用していた問題集、「合格のツボ」は解説や問題の解き方なども載っている問題集です。
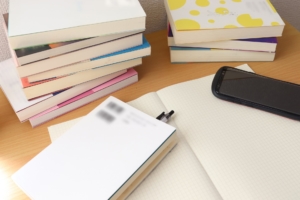
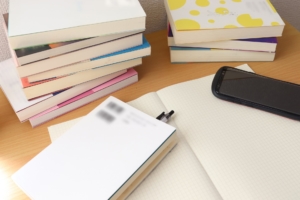
分からないところ、得意なところのくり返しになっていないか
問題集の分からないところは、繰り返し解くことになりますが、ここで勉強時間を取られるのももったいないですよね。
社会人となると日々すきま時間を活用して勉強しているわけなので、莫大な試験範囲をもれなく学習するためには、同じところをくり返し解いている時間はありません。
効率よく勉強するために予想問題を利用するのですが、問題集を買いすぎて手が付けられなくなることにも注意。
通信講座にすると必要な勉強量が絞られるので、テキストを自分で購入するよりも効率よく学習することができます。


予想問題を活用し、勉強の効率を上げよう
テキストを隅々まで覚えることは難しいことです。
「といっても、市販のテキストはコンパクトで重要事項が絞られている分、隅々まで覚えないと合格点は取れませんが」
教科数が多い試験など幅広い出題範囲がある試験には、覚えておかなくてはならない箇所を絞り込むことが大切です。
あくまで合格点を取るという勉強方法の方が、完璧に網羅しなくてもそれだけ時間の余裕が出てきますよね?
その年にあった受験対策講座の予想問題を利用すれば、受験生が覚えるべき事項を絞り込むことができるのです。


問題集の解き方について
合格体験記の中でよく聞かれるのが、「予想問題を〇周した!」という勉強方法です。
私もこの方法を真似してくり返し問題を解いていたのですが、ただそれだけじゃ点数は伸びませんでした。
ただ言われた通り、他の人の勉強方法を試しているだけでは頭に入らないんですよね。
分かる箇所、分からない箇所は人によって一緒ではないので、ノートなどにまとめる方法をとることになります。
まとめノートは試験本番前の見直しにもなりますが、前日などの超直前期にノートだけを覚えるだけになると、知識のかたよりにつながります。
直前期にどの問題を解いておくか、また、テキストの見直しに重点を置いたほうが良いですね。


まとめ
計画的に勉強することはもちろん大事ですが、計画をそのまま実行するだけでは、知識の定着に不安が残ります。
特に通信講座を利用して学習を進めている方にとっては、試験が近くなるにつれ、届けられるテキストや問題集の量が多くなり、復習の回数も限られてしまいます。
ただ、1から何週も学習することを避けるためには、重要な箇所の絞り込みやノートのまとめ方がカギとなっていくので、学習を始めた早いうちに修正をしていくことをおすすめします。
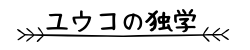
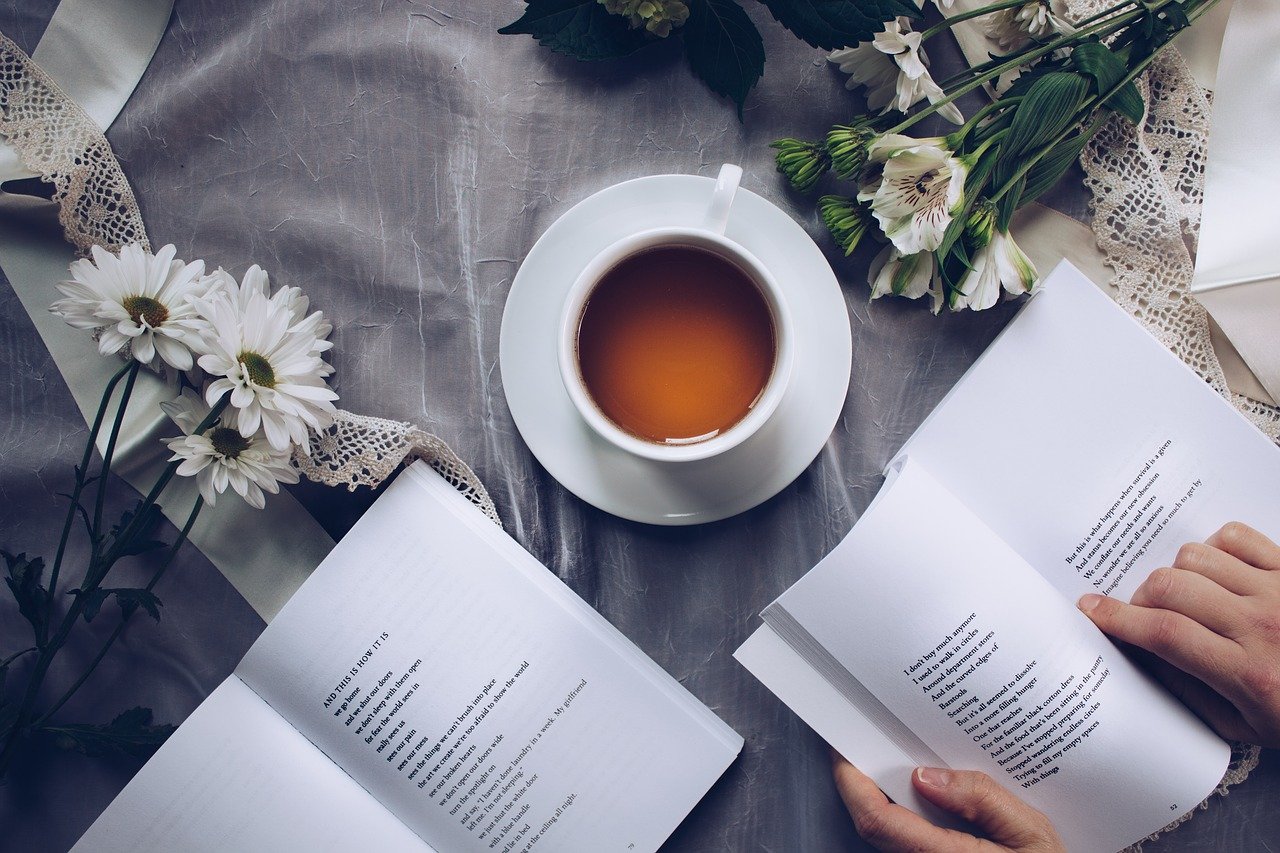



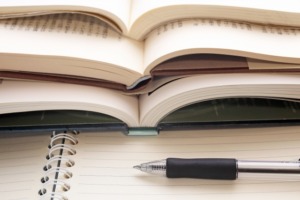

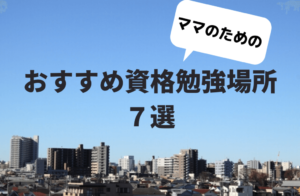
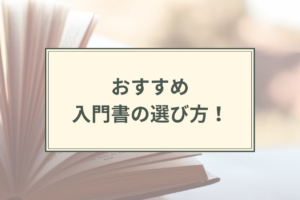


コメント