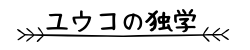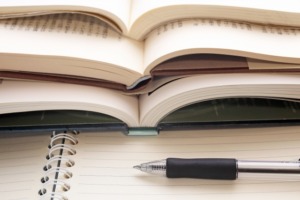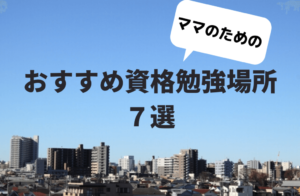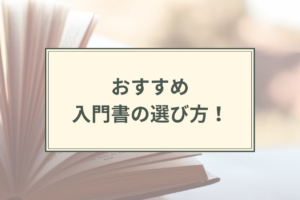資格試験のためのノートのとり方、そのまま覚えたことを書き込むだけになっていませんか?
実は資格試験ではこのノートのとり方に気をつけないと、ただ勉強しただけでその勉強時間に満足して頭に入っていなかった。ということになってしまいます。
資格試験までの限られた勉強時間で、だらだらとノートをとるだけの作業はもったいない!
ということで、効率的なノートのとり方を調査してみました。
まとめノートが作業だけになってない?そのデメリットとは
私の高校生の頃の友達で、字がとてもきれいな方がいました。その方も歴史の教科書をまとめるノートをお気に入りのペンとノートで作成していて、私もそれに憧れて真似してみたのですが、なかなか続かなかった思い出があります。
数ページしかまとめていなくて、後は真っ白…
しかし社会人になった今はノートをきれいにまとめるような時間もないし、膨大な量の法律の多い資格などではこの方法は難しいですよね。
時間のないこともこのまとめノートのデメリットですが、頭に入らずただの作業になってしまったり、結局うまくまとまっている参考書があったらそれを買ったりして、残り少ない試験までの時間を無駄にしてしまうこともあるでしょう。
また、メモをとると逆に記憶力が低下したという研究結果もあるのをご存知でしょうか。
カナダのマウント・セント・ヴィンセント大学のミシェル・エスクリットとシエラ・マーは、学生グループを集めてトランプの「神経衰弱」ゲームを用いた実験を行った。同じ絵柄の2枚の位置を記憶したあと、カードは裏返して置かれる。プレイヤーはカードを1枚めくってはそのたびに、そのカードと対になるカードの位置を思い出さなければならない。
実験では、記憶のために与えられた時間中、半数の学生にはカードの位置と正体について紙にメモをとる機会が与えられた。そのほかの学生たちは、元から備わっている記憶力に頼るしかない。また、与えられた時間が過ぎると、メモをとっていた学生たちのメモは没収されてしまう。
両グループはさまざまなカードの位置と正体についてテストされた。そして結果としてわかったのは、メモをとっていたグループの方が、カードの位置を思い出すことについて、ずっと成績が悪かった、という事実だ。
「メモをとっていたグループの方が、カードの位置と正体に関して、優れた記憶があるはずだと予測された人もいるかもしれません」と、研究者たちは語る。でもそうはならなかった。メモをとった学生たちは、記憶の貯蔵に外部形式の技術を頼るあまり、彼ら自身の神経シナプスは、何もせずにいたのだ。
つまり、メモを取るという行為で安心してしまって、記憶しようという力が働かなかった、という結果になったそうです。
しかし、記憶するという意識を持ってノートを取れば、有意義な学習をすることもできるのです。
次は効果的なノートの取り方を紹介します。
記憶に残るノートのとり方

テキストを読んでいるだけでは、インプットばかりの作業になってしまいます。
そこで早いうちから過去問を解いたり、練習問題を解くなどをしてアウトプットの作業も取り入れた方が頭に定着しやすいと言われています。

アウトプットを効果的に行うノートの取り方には、次の4つのことを意識しましょう。
- 学んだことは、すぐにノートを取らないほうがいい。
- 青いペンを使うとよい。
- 1つの単元、テーマを1ページもしくは見開きの2ページにおさめる。
- キレイに書こうと意識しない。
学んだことは、すぐにノートを取らないほうがいい。
一見してホントなの?と思ってしまいそうですが、先ほどの実験結果から分かるように作業にたよってしまわないための対策なのではないかと思います。
覚えたことを一旦頭で整理してから、考えたことを自分の言葉で書き出していく。そうすることで知識の定着があがっていくのかもしれません。
青いペンを使うとよい。
こちらは色彩の効果で「青」が心を鎮める効果がある、ということなのだそうです。
学生の頃、ただ青いペンで書くことがかっこいいという気持ちで、手紙や手帳を青いボールペンで書いていましたが、きちんと根拠のあることだったんですね。

1つの単元、テーマを1ページもしくは見開きの2ページにおさめる。
あらかじめまとめる範囲を決めておくことで、テキストの内容をそのまま書き写すだけでなく要約してまとめる力を付けることができるそうです。
その要約したプロセスが、記憶に残る、ということなんですね。
キレイに書こうと意識しない
作業を楽しむのではなく、意識するのはその内容ですよね?ノートをとることを目的としない、ということです。
さらに応用したいノートの活用法
効果的なノートの使い方の応用編として、2つの方法を紹介します。
ふせんを利用したノートの活用
こちらは以前も紹介しましたが、さきほどのノートを1ページにまとめるという方法の中で、さらにわからないところなどをふせんに書き込むことにより、わからない箇所の整理ができるところがメリットです。
ふせんを色分けして、覚えておくことの重要度を分けてみることもいいですよね。

勉強した記録をつけるだけのノート
こちらは簡単で、覚えておくことを書き留めるのではなく、勉強時間を視覚化する方法です。
1日の勉強時間をどんな単元を勉強したのかをマーカーで色分けしておくと、わかりやすくなります。
こちらは手帳に書き込む方法でも良さそうですね。

過去問解説をまとめられるノートが使いやすい!
資格試験の通信講座、フォーサイトでは、問題演習のためのノートがセットでついてきます。
これがわざわざ線を引いてまとめノートを作らなくていいし、問題ごとに自分なりの覚えておきたいことやテキストのページ数を入れることができるので、簡単にノートをまとめることができます。
まとめ
ノートをまとめるには、そのまとめるときの時間や、書くときにも要約するなど頭をつかうことにより、ただ作業をしている感覚をなくすことが大事そうですね。
またふせんやマーカーを利用すると、試験直前の時期に見直すときにうまく整理ができそうです。
ノートをまとめた満足感より、活用できるノートを目指しましょう。