青ペンで書きなぐる勉強法。
私は今までこの勉強方法をとっている方をチラホラ見かけたことがあります。
かといって、ボールペンのみを使用したノートのまとめ方は試したことがあるのですが、青いペンですべてを書きなぐる、といったことはしたことがなかったんですよね。
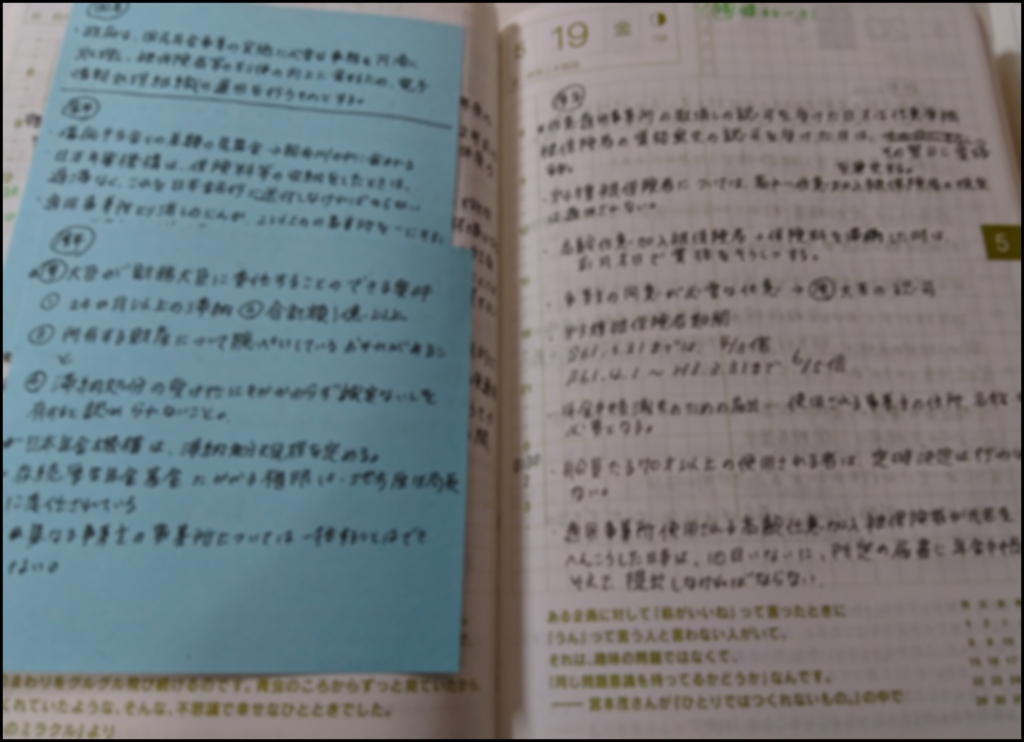
ボールペンでノートをまとめると、そのノートの出来上がりももちろん記録となり自信につながりますが、中身が見える透明なボールペンを使うことによって、インクの減り具合でその進捗度が測れるといったメリットもあります。
私の場合、ボールペンの芯の詰め替えができるものを使っていたので、勉強を始めてからボールペンの芯を試験が終わるまでずっと持っていました。
使い切ったボールペンの芯の本数が増えることによって、勉強に対する達成感が得られる、というわけです。
青いペンがもたらす心理効果

日本ではあまりよく見かけませんが、欧米では契約書のサインや、万年筆のインクでも「青」を使うことがあります。
日本は墨の文化と言われているので、やはり黒を使う機会が多くなります。
私ごとですが、銀行の引き出し伝票のサインを青で書いたときに、「それは使えません」と窓口の人に言われたこともあり…
日本人にとっては勉強をするときにも「青」を使うことによって、新鮮な気持ちでモチベーションを保てるというところもあるのでしょうね。
そんな青いペンには主にこんな心理効果があるそうです。
- 気持ちを鎮める、癒し効果
- 集中力を高める効果
気持ちを静める癒し効果
青色は寒色、鎮静色ともいわれ、海や空をイメージさせる色。
感情や精神をコントロールし、気持ちを落ち着かせる効果もあります。
日本人にとっては勉強の時に青いペンを使うことによって、新鮮さを保つことができそうですが、ヨーロッパでは子どもたちでも青を使うことを基本としているようです。
子どものころの青ペンの使い方といえば、問題集やテストの時に、二回目に○をもらったり、忘れてはいけない箇所をメモしたりということがほとんどだったと思います。
しかしヨーロッパでは、授業でノートをとる時にも青いペンを使っているそうです。
気持ちを落ち着かせる効果を古くから活用していたということになりますね。
集中力を高める効果
私は中学生の時に吹奏楽部に入っていたのですが、楽譜には吹きかたの強弱や音の切り方などをメモするときに、主に青のペンやマーカーを使ってまとめていました。
吹奏楽部に入っていた方ならあるあるですが、楽譜の中をマーカーで自分なりに汚していくのが楽しかったんですよね。
当時はそんな意識はしていませんでしたが、青いペンを使うことによって楽しくとも厳しかった部活生活でも気持ちをコントロールしていたのでしょう。
演奏するときもその青いペンで注意書きを書いた、もはや色付けした楽譜をみながら吹いていくので、知らないうちに集中力がついていたのでは?なんて思っています。
赤い文字(赤いインク)の心理効果


テストでのチェックや重要な箇所を赤いペンで書いていくことは多くあると思います。
そこで、赤い文字(赤いインク)の心理効果を調べてみると、
- 気持ちを高ぶらせる
- 注意を引く
などが挙げられます。
アドレナリンの分泌を促進させ、興奮させる色。
なので、ノートをまとめるときには赤い文字ばかりだと疲れてしまうのです。


ただ、テキストにもよくあるように、重要な用語などは赤い字で書かれていますよね。
目につく色なので、どうしても覚えられない用語や単語を覚えておく時には、赤いペンで書くとよいでしょう。
暗記シートの活用法
ペンの色を変えることによって、暗記するときにはシートを使って覚えることができますよね。
一番よく見かける暗記シートといえば、赤いものだと思います。
しかし長時間暗記作業をするならば、鎮静色である青いシートのほうがいいのではないかと思ってしまいますよね。
青の暗記シートがないのはなぜ?
こんなに青い色の鎮静効果が言われているのに、青の暗記シートはあまり売られていませんよね。
そこで、青のシートがどうしてないのかを調べてみると、青のシートがないのは、かなり低い色合いにしなくてはならないので、周りの黒も消えてしまう。ということらしいです。
ただ、青い色で文字を隠して暗記するタイプはありますね。
こちらの商品は、青いシートがふせんになっていて、重要な文字にこの青いふせんをちぎって貼って使うタイプになります。
暗記目的でなく、ざっと文章を追う時には青の効果で集中力が増すのではないのでしょうか。
まとめ
青い色の文字やペンの効果は、暗記用でなく普段のノートをまとめるときにありそうです。
数年前に流行ったこちらの勉強法でも、青ペンで書きなぐることを推奨しています。
私は青ペンではありませんでしたが、ペンでノートをまとめることはとてもやりがいがあります。
皆さんも試してみてくださいね。
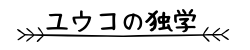




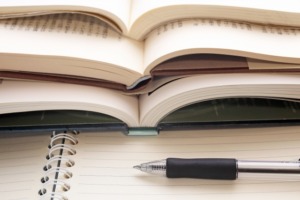


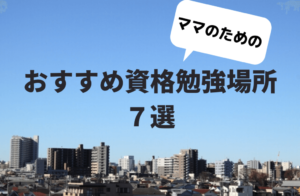
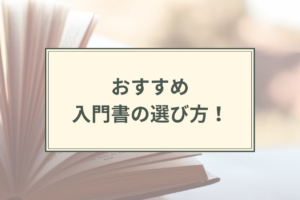


コメント