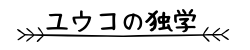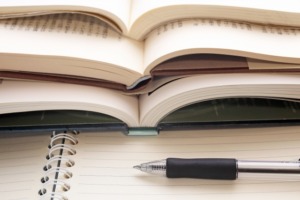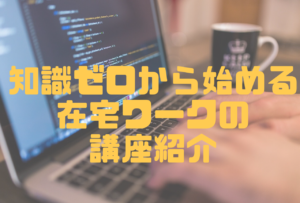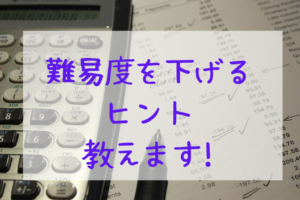日商簿記3級は、職歴にブランクのある方や就職活動を始めるときに一番注目されている資格じゃないでしょうか。
それゆえ、主婦や学生でもこの資格に挑戦する人が多く、また独学で取れる資格として人気ですよね。
この資格に必要な勉強時間を調べてみると、短期間で出来るというものから最長で3ヶ月を要するなど、いったいいつから始めるのがいいのかわからないくらいですよね。
今回は私の経験も踏まえて、この資格におすすめの勉強法や資格をとった後にどう活かすことが出来るのかを紹介していきます。
日商簿記3級は就職活動のときにおすすめされやすい
思えば私も離婚してもう一度就職活動を始めたときに、職業安定所の相談員からすすめられたのがこの資格でした。
このときは「簿記?経理なんてそんなに興味ない…」と思っていたのですが、しかしなんとかして早く就職できるなら…という思いで薦められるがままに勉強を始めたことを思い出します。
そういえば、市役所で母子医療助成の申請に行ったときも、就職あっせんのパンフレットをもらい、そのなかでもこの資格の講座案内があったほどです。
そこで毎回の受験者数を調べてみると、
- 第142回(平成28年2月) 114,940名 合格率26.6%
- 第143回(平成28年6月) 106,558名 合格率34.2%
- 第144回(平成28年11月) 120,096名 合格率45.1%
- 第145回(平成29年2月) 105,356名 合格率47.4%
と、毎回10万人超えの受験者数で、2~3人に1人は合格している、といった感じですね。
ただ統計をみただけでも、一回受験経験のある人とそうでない人ではその試験の雰囲気や時間配分の経験などで差が出てきますよね?
そういえば本試験の雰囲気、独特でした。後述しますが試験の最初の問題は電卓を使わずに解ける仕訳の問題からはじまるのですが、このときは鉛筆の音だけが。だんだんと時間が経つにつれ、電卓を使う問題が増えてくるので、電卓を叩く音が強くなっていくんですよね。
そして、特に電卓を叩く速さが早い人がいると、若干怖気づくこともありましたね。
そんな本試験の雰囲気にも負けないよう、充分に勉強していくわけですが、まずこの簿記3級の勉強を始めるにあたっていちばん重要なことは、勉強時間をどう設定するか、それとテキスト選びになっていきます。
【簿記3級勉強法】時間配分とテキスト選び

私がトータルで勉強した時間は記録していないので覚えていませんが、勉強時間についてはスクールや通信講座を利用するときの時間と、独学で勉強するときの時間では大きな差があるようです。
おすすめの勉強時間は結局試験日までの期間
通信講座やスクールで簿記3級を勉強するなら、トータルの勉強時間は約100時間と設定されているところが多いです。
期間は2~3ヶ月。1日の勉強時間は1~1.5時間といったところですね。
しかし、試験勉強をされた方なら誰でも分かる通り、試験日に近くなるにつれて1日の勉強時間は増えていきがちになります。
なので、計画を立てる際は均等に1日の勉強時間を決めておいてもそのように行かないケースが多いと思います。
逆に、独学なら1~2週間で勉強が完了する、と言われることもあります。
当然この場合はまとまった時間が必要となりますし、勉強のスタイルも変わってくることでしょう。
本屋さんで売っているテキストでの独学と、スクールで学ぶ場合では、前者はあくまで試験の合格点を取るまでの知識を得ること、後者ではさらに深く学ぶことができある問題に対してその根拠も学習するので、知識の定着ではスクールのほうがつきやすいと思います。
実際私は3級受験では独学、2級受験ではスクールで勉強しましたが、深い知識で定着が早かったのはスクールの方かなと感じました。
今回は試験の合格を目標としての勉強法を紹介します。
テキストは問題集と連動したものを
本屋さんで売られている日商簿記3級のテキストは簡単な漫画つきのものから教科書ライクで文字の色が黒と赤の2色刷りのものと色々なテキストが売られていますが、まずは「○日で合格」などといった表紙のタイトルにまどわされないほうがいいですね。
というのは、本屋さんで売られているテキストはその内容を100パーセント覚えた時点でやっと合格点が取れるというものが多いからです。
中身を確認して自分が勉強しやすいものをということは当然ですが、書き込める余白のあるものをおすすめします。
また、テキストと連動した問題集を使うこともおすすめです。覚えた内容をすぐに問題を解いて力試ししたいときに、すぐに問題に取り掛かることができる体制をとり、テキストと内容を合わせている無駄な時間をさけたいからです。
スキマ時間はアプリを使って有効活用
毎回10万人もの受験生がいる試験ですから、最近ではスマートフォンのアプリも充実しているようです。
スマートフォンはスキマ時間を活用するときに使用できますね。一つはダウンロードしてもよさそうです。
こちらの動画授業サービスも、簿記3級の学習ができるコンテンツが揃っています。
【簿記3級勉強法】実際の問題を分析してみる

出題傾向はこんな感じ
日商簿記3級の試験問題の傾向にはパターンがあります。大問1から見てみましょう。
- 第1問 仕訳問題 5題
- 第2問 売掛、買掛金元帳や現金出納帳などの各帳簿の記入
- 第3問 試算表
- 第4問 伝票の会計、もしくは訂正仕訳等
- 第5問 精算表
第4問はその試験の回によって出題される内容が若干変わってきますが、大まかに言えば第1問からの流れは、毎日の業務から決算時に行う精算表まで、1年の事業の流れと合わせていることがわかります。
※とはいえ、細かい数字が内容が前の問題から続いているわけではありませんが…
先ほど本試験の雰囲気をお伝えしましたが、この第1問の仕訳問題は電卓を使う必要のない問題なので、徐々に電卓を叩く音が響いてくる感じはここにあったんですよね。
テキスト選びでは連動した問題集も必要なんですが、一通り問題を解いたら過去問題集も買い、3~4回分は時間を測って解いておくこともおすすめします。
試験問題は一つの事業の1年の会計の流れと捉えておいて、「さて今回の精算表はどんな感じかな?」なんて楽しむくらいにしておくと、その時点ではもう合格ラインは超えてるレベルに達していますよ。
2019年度の出題範囲の変更について
2019年度から簿記3級の出題範囲が変更されたのですが、やはり気になるところは、「難しくなったの?」というところですよね。
しかし今までの出題範囲からなくなった問題もあるようなので、レベルがあがった、というわけではなさそうです。
大まかにどういうところが変更されたのかというと、
- 「個人商店」から「小規模の株式会社」の会計を考えた問題範囲
- 電子記録やクレジットなど、紙ではなく電子化された内容の問題出題
の2つに分けられるそうです。
「小規模の株式会社」を考えた出題範囲なので、ここには当然、個人商店で問題になっていた、所得税の問題や、純損益の資産への振替の問題がなくなりました。
また、実は私が個人的にこの試験勉強で悩まされていた、手形の裏書譲渡や割引の問題が2級以上の範囲となったので、人によっては簡単になった?と感じる人もいるかも知れません。
【簿記3級勉強法】取得した資格を今後活かすには
日商簿記3級の試験は今まで通り紙と鉛筆で行うものですが、実際の実務となると、会計ソフトを使うところが多くなりますよね。
この理由は年々税制度が変化していって、そのたびに新しい情報を取り入れることになるので、その情報を常に更新できる会計ソフトでないとスムーズに対応しにくい、という点があるからです。
それゆえ、パソコンの基礎知識は同時に知っておきたいものですよね。
FOM出版「よくわかる」シリーズは緑の表紙でおなじみのテキストです。
MOS検定試験「マイクロソフトオフィススペシャリスト」を取得するときにも読まれている参考書になります。
また、実際に財務諸表を見る時にどんな変化があったのか、傾向を見ることもあります。
簿記検定に合格したら、財務諸表を読める能力がつきますので、その分析も出来るようにしたいものです。
まとめ
日商簿記3級試験を独学で資格取得するなら、まずはテキストや問題集選びが重要。そして、1年の会計の流れをつかめるように過去問を使って練習することが大事になっていきます。
1つ資格を習得すると、それに合わせたさらに上級の学習にも興味が湧いていきます。
そのような情報もこちらで紹介できたらなと思います。