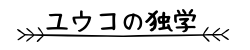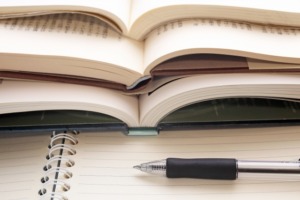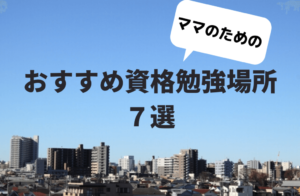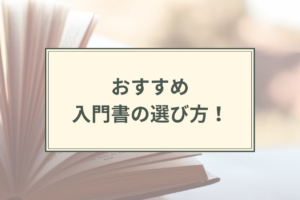資格試験の合格体験記によくある過去問の繰り返し勉強法。資格の勉強をされた方ならこの勉強法は経験したことがあると思います。
過去何年分を解くのかや何回繰り返すのかなど、合格された方と同じ数をこなせば合格できる!と自信がつきますよね?
しかしその量だけを勉強すればいいのではなくて、過去問の解き方は最低限の2つのあることを意識しないと時間だけが過ぎてしまって、無駄な勉強法になってしまうのです。
実は私がそのことに気づかずに失敗してしまったんですよね。
今回はその失敗談から分かったことをまとめました。
失敗1:答えを覚えてしまう

一番陥りやすい原因は、過去問を繰り返しているうちにその問題の中身を覚えずに答えの選択肢を覚えてしまうということです。
こうなると何回繰り返し勉強しても意味がありませんよね。
しかし前提として、過去問の繰り返し勉強法は決して悪いというわけではありません。むしろ効率の良い勉強法ともいえるし、通勤中など何かのスキマ時間に行うには勉強しやすい方法です。
解けたところ、解けなかったところを整理することによって勉強の進み具合が分かります。
過去問を解き始めるタイミングは?
初めて資格試験に挑戦する人が陥りやすい無駄な勉強法として、一通りテキストを読んでから問題を解いてしまうということがあります。
比較的簡単な資格試験ならこの方法でも大丈夫ですが、宅建試験や社労士試験、行政書士試験などのいくつかの法律が出題される試験ではこの方法では通用しません。
勉強が進んでいくうちに過去に覚えたものを忘れて行ってしまうんですよね…
よく言われる「エビングハウスの忘却曲線」、これはドイツのエビングハウスという心理学者が研究した、時間とともに人の記憶がどのように忘れていってしまうのかということを表した曲線です。
反比例でだんだんと減っていくグラフは、時間の経過とともにどれくらいの記憶が消えていくかを表しています。
覚えた内容の…
20分後には42%忘れる
1時間後には56%忘れる
1週間後には77%忘れる
1か月後には79%忘れる
と言われているので、覚えた範囲の内容をなるべく早く復習するために、過去問は早くから取り組んだほうがいいと言われているんですね。
上記の結果から、1日経つと半分以上忘れてしまうということが分かります。
なので、繰り返すタイミングとしては、
1日後、3日後、7日後、15日後、20日後・・・
がベストと言われています。
答えを覚えてしまわないために
過去問の答えだけを覚えてしまわないために気を付けたいことは、
- 繰り返す時に順番を変えてみる
- 問題の意味が分からないときはテキストで復習
という方法が取れると思います。
択一式の問題では答えだけを覚えてしまうと、4~5択あるうちのほとんどを覚えなくなってしまうので、問題文一つ一つを読むためにも、○×式、一問一答式の問題集を使ったほうが良さそうですね。
主な一問一答式のおすすめ問題集はこちら!
また、こちらで紹介している通信講座にも一問一答式のアプリが充実しています。

失敗2:出題パターンを過信してしまう

○×や選択肢の答えを覚えていなくても、問題の出題パターンを覚えてしまうと応用が利かない、ということにも陥ってしまいます。
どういうことかと言うと、まずは例を出してみましょう。
適用事業所に使用される1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上であるパートタイマーは、健康保険法第3条第1項に掲げる適用除外事由に該当しなければ、被保険者となる。
こちらは社会保険労務士試験、健康保険法の被保険者となるパート従業員の問題です。
この問題は○となるのですが、この規定は平成28年10月から改訂されたものとなります。
しかし平成28年10月以前にこの要件を満たさなくても、前から健康保険の被保険者となっていた場合は引き続き被保険者となるので、この問題が少し変わると×問になる可能性もあるということですよね。
単なる数字の違いなどでは間違いは起こりませんが、きちんと問題を読まないと不正解になってしまうこともあるので、問題の周辺にある事項をテキストで見直すことは、試験本番の直前でも行わなければいけない作業となっていきます。
効率の良い過去問勉強法のまとめ
過去問の繰り返しは勉強が進むにつれてその範囲が多くなっていくことから、勉強を途中であきらめ受験しなくなるということも多く起こっているそうです。
実際、受験をあきらめ今年受験のテキストや問題集をメルカリで販売している人も多く見かけます。
過去問の繰り返しは効率がいい勉強方法ですが、落とし穴もあるということを覚えておいてくださいね。