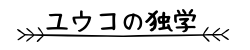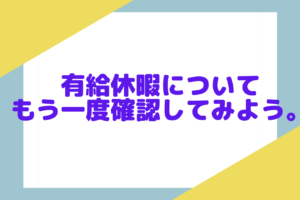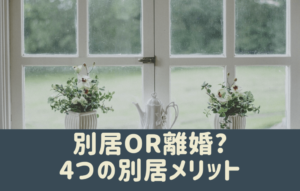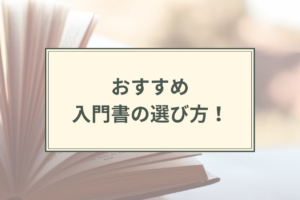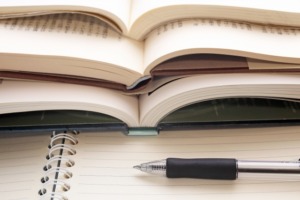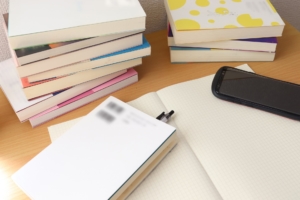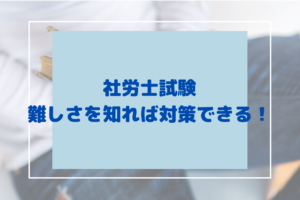有給休暇を利用して、子どもの保育園や学校の行事に出かけるシングルマザーは多いと思います。
しかし有給休暇はどれくらいとれるのか、買い取りはしてくれる?など、詳しく知らない方も多いのではないのでしょうか?
今回は、
- 有休休暇はどれくらい貰えるもの?
- 有休休暇は買取できる?
- パートにも有給休暇はある?
- 知ってた?有給休暇や労働時間の法律は一つじゃない!
など、有給休暇についてのあれこれを解説して行きたいと思います。
今回は社労士試験の試験範囲にもかかわるので、勉強にもなると思いますよ!
有給休暇の買い取りにはさまざまな条件があります。

まず、法定の有給休暇の買取は原則としてできないとされています。
これはどういうことかと言うと、会社で労働者を雇う、雇われるために作られた法律「労働基準法」で定められている有給休暇は買取できない、ということなんです。
有休休暇とは、労働者に心身のリフレッシュをしてもらおうということが目的。
休暇を取ってもらうことが目的なので、会社がお金に換えて支給することはその目的に反しているということなのです。
しかし、「労働基準法」は最低限守りましょうという法律なので、もともと会社が労働基準法の規定を越えた日数の有給休暇を与えている場合は、労働者が退職するときなどに会社が買い取ってくれることもあります。
このような有給休暇の規定は、会社が作成する「就業規則」に書かれているので、もし退職時に有給休暇を使っていないなと思う時には就業規則を確認するといいでしょう。
もしくは、上司に確認するのもいいですね。
しかし会社が必ずしも残った有給休暇を買い取りましょうという決まりもないので、会社にそのような規定がない場合は買い取りもありません。
有給休暇の取得条件について
それでは、労働基準法で定められている有給休暇の日数はどれくらいなのかを紹介する前に、有給休暇の取得条件を確認してみましょう。
先ほどから「有給休暇」という名前を使っていますが、会社や人によっては「有休」とか「年休」という言い方もしますね。
原則として会社は入社から6か月間の勤務の中で、与えられた労働日の8割以上出勤している労働者に対して、有給休暇を10日間与えることとなっています。
その後1年ごとに与えられる有給休暇が少しずつ増えていくのですが、労働者に与えられる有給休暇の時効は2年間までとされています。
ここも2年間で使いきれなかった分を買い取りすることが認められています。
有休休暇の付与日数
| 勤続年数 | 与えられる有給休暇の日数 |
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
上記の日数が、法律で最低限定められた有給休暇日数となります。
入社して6か月後に10日間、その後、1年ごとに1日、2日増え、入社して6年6か月を過ぎるとその後は1年ごとに20日間付与されることになっています。
会社によっては、この日数以上の有給休暇を定めていることもあり、その場合に買取りできるとされています。
新しく改正された有給休暇の義務化について
働き方改革により平成31年4月から改正された「有給休暇の義務化」では、社員が先ほどの表で与えられる有給休暇の日数よりも少なく休暇を取っていて、消化日数が5日未満の場合は、会社のほうから休んでくださいとお願いするということを義務化するということです。
ここは会社の規模に関係なく義務となっているので、もし上司の威圧で有給休暇を申請することができない、といったことがないように保護されています。
ここは新しい制度なので、上司が知らなかったということもあるので働く上では覚えたほうがいいところです。
パートの有給休暇について
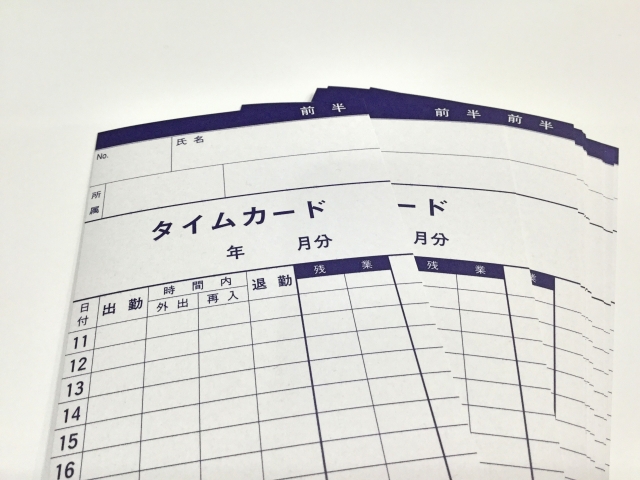
パートやアルバイトで会社に雇われていると、有給休暇はないものだと思われがちになりますが、実は法律上有給休暇は決められています。
先ほど紹介した付与日数よりも少ないのですが、次の条件に当てはまる人は、1週間の出勤日数によって比例して有給休暇が付与されるものとされています。
対象となる人は、1週間に決められている労働時間が30時間未満であり、かつ、
- 週の所定労働時間が4日以下の人
- 1年間の所定労働日数が216日以下の人
労働時間が30時間以上になる場合は、最初に紹介した日数が付与されます。
パート方の有給休暇付与日数
| 勤続年数 | 週の所定労働日数(1年間の所定労働日数) | |||
| 4日(169~216日) | 3日(121~168日) | 2日(73~120日) | 1日(48~72日) | |
| 6か月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
| 1年6か月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 2年6か月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3年6か月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
| 4年6か月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
| 5年6か月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
| 6年6か月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
こちらも入社して6か月目から有給休暇が付与され、それまでに8割以上の出勤が条件となります。
また、申請しても有給休暇がもらえない場合として法律上では「事業の正常な運営を妨げる」時に会社は有給休暇の申請を拒否できるとあります。
有給休暇を取った時の賃金はどうなるかと言うと、その日に働く予定だった時間×時給分となりますね。
買取りができると勘違いされるのはなぜ?
冒頭に説明した通り、法律上の有給休暇は原則として買い取りできないのですが、ネット上の質問サイトなどでは買い取りできるとの回答が多くみられることがあります。
なぜそのようなことが起こっているのかと言うと、やはり買い取りできるかどうかについてはその会社によって規定が違うからなんですね。
自分の働いている会社の感覚で回答してしまうので、一般的に「有給休暇は買い取りできる」と思われてしまうのです。
公務員はそもそも労働時間が違う場合がある
会社と労働者が対等な立場でいられるために作られた労働基準法ですが、一般職の国家公務員は適用が除外され、また一般職の地方公務員についても一部適用が排除されています。
それぞれ別の法律で定められているんですね。地方公務員についてはそれぞれの自治体の条例によって定められた労働の法律に違いがあります。
有給休暇についても付与のしかたが違い、改正された最低5日間の付与義務についても、公務員は除外されているのです。
また勤務時間についても、臨時や緊急の事態がある場合は各省庁の長の判断により、勤務時間を延長して労働させることができるとされています。
一見して休みがしっかりとれるイメージの公務員ですが、職種によってはハードな面もありますよね。
一般的な公務員の有給休暇の付与日数は、1年目から20日間取れるとよさそうな面もありますが、なんとなく公務員になってしまって痛い目に合う人も多いのでしょうね。
まとめ
今回は有給休暇についてあれこれ紹介しました。
社労士試験の中での有給休暇の問題については、他にも時季変更権や時間単位で有給休暇がとれるのかなどの問題があります。
これらの細かい論点を理解するためにも、下記で紹介されている通信講座の使用をおすすめします。