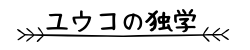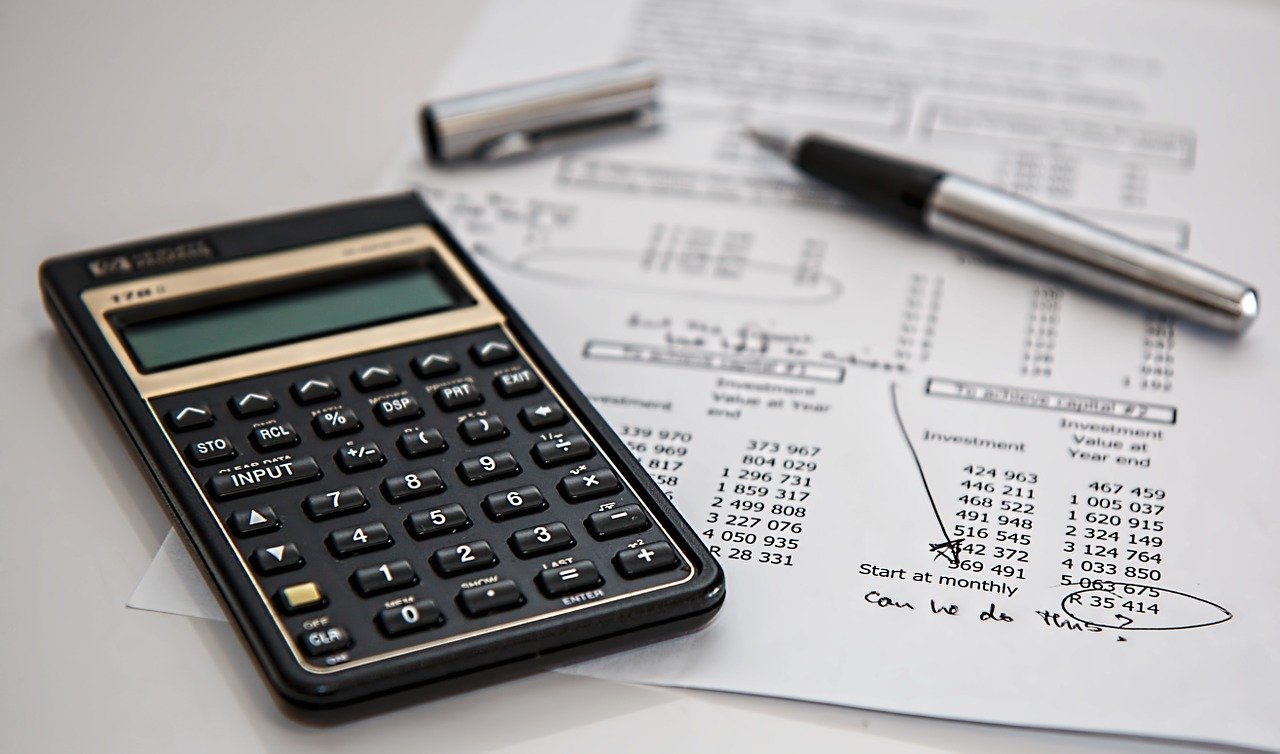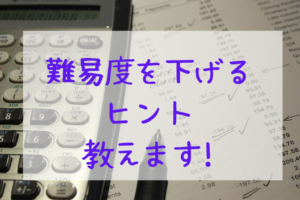私が日商簿記3級の勉強をしていた時に一番分かりにくかった事項、手形の裏書譲渡の覚え方について解説していきたいと思います。
いきなり難しそうな言葉から始まりましたが、順を追って考えていけば簡単な取引です。
また、こちらは簿記3級の範囲ではないのですが、この「手形」が使えなくなった時の「不渡手形」の話が興味深い内容だったので紹介していこうと思います。
独学で日商簿記3級を勉強される方は、市販のテキストと一緒にこちらの動画サービスを申込すると、より一層理解が深まります。
また、仕事に役立つ動画も配信しているので、お得なサブスクサービスです。
裏書譲渡を覚えるならまず手形の取引の話から
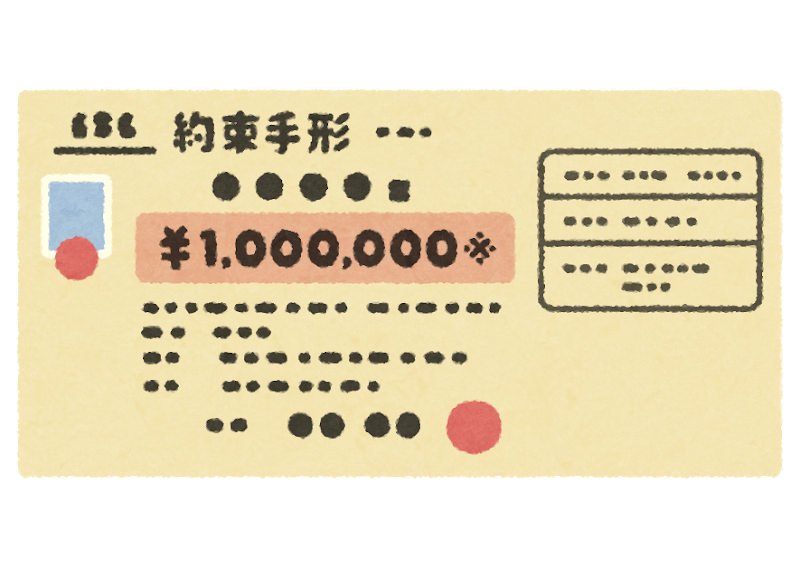
裏書譲渡とは手形を利用するやり取りの一つとなりますが、この手形は通常なら商品の売買や掛代金のやり取りのときに現金や小切手の以外に用いられる方法となります。
手形には、「約束手形」「為替手形」の2種類があります。
- 約束手形とは
一定の期日に一定の金額を自ら支払うことを約束した証券のこと。二者間の債権・債務を決済するときに利用されます。 - 為替手形とは
約束手形とはちょっと違った証券で、一定の期日に一定の金額を受取人に支払うことを依頼することができる証券。三者間のやり取りとなります。
裏書譲渡とは、この「約束手形」を使ったやり取りとなります。
約束手形というと、子どものころに遊んだ人生ゲームを思い出しますよね。
ちなみに昨日は人生ゲームナイトでした。
写真の意味がわかるかね。
ただ持って撮ったんじゃないんだ。そうだ。借金地獄だ。#人生谷だらけの人生ゲーム#約束手形#前代未聞の35枚#詰んでた#ただ詰んでたおかげで価値無くなりかけてたお宝を精算出来たという#複雑な人生 pic.twitter.com/n55mADruK3
— 賀駒さくり-Kaku,Sakuri- (@4aiofollowme) 2019年10月2日
この時は確か、手元に現金がないときに銀行役の人からこの紙をもらって、沢山たまると「ああ~負けた~」となるゲームでしたが、実際の約束手形はそんなシビアな事情ではありません。
手形に記入された支払期日に、自分の当座預金から相手にそのお金が入金されますからね。(ただ当座預金の残高が越えてたらって話もありますが…)
実際の仕訳問題ではこんな感じ
この手形を使ったをやり取りを試験問題として出されたときは、このような感じになります。
A商店は、B商店から商品10,000円を仕入れ、代金はB商店宛の約束手形10,000円を振り出して支払った。
手形を渡すやり取りは、「振り出す」という言葉を使うんですね。
この時の仕訳としては、
(借)仕入 10,000/(貸)支払手形 10,000
となります。
逆に、B商店からの視点として、
B商店は、A商店に商品10,000円を売上げ、代金は同店振り出しの約束手形10,000円を受け取った。
という問題が出たとすると、
(借)受取手形 10,000/(貸)売上 10,000
と、同じ証書のやり取りでも勘定科目が変わっていくんですね。
また、約束手形にかかれている支払期日が到来すると、このような仕訳となります。
A商店は、かねて振り出していたB商店宛の約束手形10,000円が、期日に当店の当座預金口座より支払われた旨を、○○銀行から通知を受けた。
仕訳としては、
(借)支払手形 10,000/(貸)当座預金 10,000
一方、B商店の取引としては、
B商店は、かねて取り立てを依頼しておいたA商店振り出しの約束手形10,000円が、期日につき当店の当座預金口座に入金した旨、取引銀行から通知を受けた。
(借)当座預金 10,000/(貸)受取手形 10,000
となります。
勘定科目が変わっていくところがポイントですが、実際の試験問題の仕訳問題ではその勘定科目は問題から選ぶかたちとなります。
とはいえ、それぞれの勘定科目については一つ一つ覚えていったほうがいいので、しっかり意味を確認していきましょう。
こちらの記事もお読みください。


裏書譲渡とはどういうやり取り?

さて、ここから本題の裏書譲渡の話となります。
裏書譲渡は簡単に言うと、先ほどの約束手形(為替手形でもOK)の支払い期日を待たないで、その手形を他人に譲り渡すやり取りとなります。
このとき、手形の裏面に「表の金額を被裏書人(譲り渡す相手)またはその指図人にお支払いください」と書かれている欄があるので、そこへ必要事項を記入し、被裏書人に渡します。
この時のやり取りを試験問題とすると、
B商店は、C商店から商品10,000円を仕入れ、代金はかねて受け取っていたA商店振出当店宛の約束手形10,000円を裏書譲渡した。
となり、仕訳は、
(借)仕入 10,000/(貸)受取手形 10,000
となります。B商店から見ると、先ほどの約束手形が移動するということになるので、「受取手形」の勘定科目になるんですね。
また、C商店では、
C商店は、B商店に商品10,000円を売上げ、代金はA商店振出、B商店宛の約束手形10,000円を裏書譲り受けた。
となり、
(借)受取手形 10,000/(貸) 売上 10,000
となります。
銀行に裏書譲渡する、「手形の割引」
手形は支払期日前に、取引銀行を被裏書人として換金することもできます。
支払い期日の前に換金するのですから、その期日からの日数を割引されるので、「手形の割引」と言われます。
C商店は、さきに受け取っていたA商店振出の約束手形(支払期日 12月10日)10,000円を取引銀行で割引き、21日分の割引料100円を差し引かれ、手取金は当座預金とした。
となると、仕訳は、
(借)当座預金 9,900/(貸) 10,000 手形売却損 100
となります。
ということで、裏書譲渡という名前だけでは難しい言葉のように見えますが、勘定科目の使い方を覚えていけば、そんなに難しくはない、ということがお分かりいただけたと思います。
ところで、ここからは日商簿記3級の範囲ではないのですが、もし手形に書かれていたお金が引き渡されないときにはどうなるか、を調べたので紹介したいと思います。
手形の不渡りってやばいことなの?
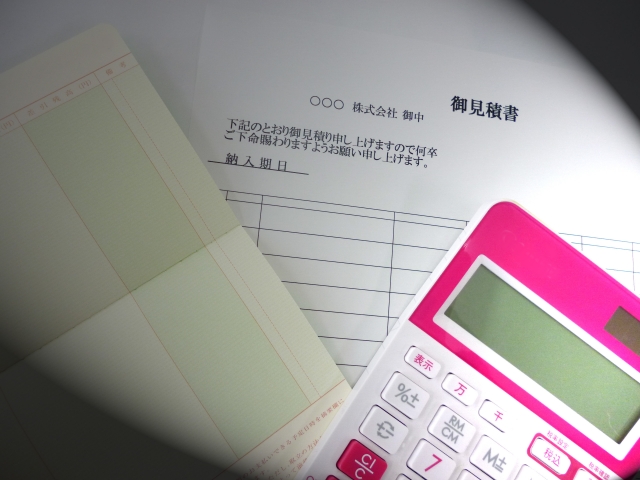
「手形の不渡り」とは、先ほどの手形の支払い期日を過ぎても、債務者(振り出した人)から債権者(手形を所有している人)へ額面の金額が引き渡されず、決済できないことを言います。
決済できないという知らせはまず、地方にある「手形交換所」から加盟する銀行へ通知されます。
手形交換所とは
加盟する金融機関が定時に一定の場所で約束手形や小切手を持ち寄り、決済や交換を行う場所のこと。
手形を振り出した会社の取引銀行に通知が来るのですが、ここで1回目の不渡り通知だと、銀行は要注意の会社とみなし、手形の割引などの取引は拒否することになります。
しかし、1回の不渡りだけでは「倒産」と見なされず、当座預金は使えることになっています。
その後、6か月以内に2回目の不渡りを出すと、銀行の取引もすべて停止となり、手形も使えなくなるそうです。
そもそも実際の取引では約束手形の振出はその商品を仕入れた日後、取引先の締め日が過ぎて請求書が来てから行われ、支払期日も120日など長いものもあるので、かなりの時間が経過していることになります。
支払う側にとってはかなり後からの出金になるので、計画的にお金を用意しておかなければならないということなんですね。
まとめ
日商簿記3級の範囲の一つ、手形の裏書譲渡については勘定科目の意味を理解し、流れをつかんでいくことで簡単に覚えられると思います。
ここに書かれたことが誰かの試験に役立てればと思い、まとめてみました。