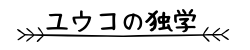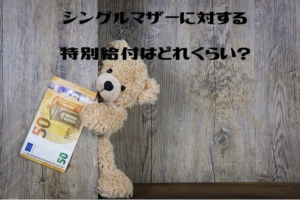今回は私が行った離婚までの準備と覚えておきたい支援制度のお話をしようと思います。
どんなに準備しても離婚した先は見えないもの。
制度やテクニックを覚えて、できるだけお金をかけずに後悔しない離婚をしたいものです。
離婚準備は入念に!

まず、お金をかけずに離婚準備を行うには第一に計画をきちんとたてること、第二に情報を集めることが大切です。
相手を待たせたり、また相手に都合がいいように流されないためにも、準備を怠らないようにしましょう。
計画をたてる理由
離婚準備には、弁護士さんなどの専門家の意見は必ず聞いておきたいものです。
しかし、専門家の人たちも商売として相談を受けているのですから、感情的な愚痴などで無駄な時間を過ごさないようにしたいもの。
そこで事前に、相談したい内容をメモしておき、内容を整理しておきましょう。
限られた時間の中で、聞きたいことをきちんときいておかないと、もう一度相談する事になり、相談料が無駄にかかってしまいます。
自分から申請しないと制度は受けられない
これから紹介する制度は基本的に自分から申請しないと受けられません。
また、申請期間のあるものや、受けられる支援のタイミングで入金が遅くなることもあるので、知らないでおくとそれだけお金が支払われ、生活に影響が出ることもあるので、覚えておきましょう。
私が行った離婚準備を教えます!

まずは円満に離婚を解決するための方法として、財産分与、慰謝料、養育費をきちんとすることが考えられます。
これらをはっきりするために
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
の方法がとれます。
私の場合は既に別居していたのですが、連絡は取れる状態、しかし面と向かって長いこと話すと体調が崩れてしまうような状態でした。
しかし電話やメールはやり取りできたので、上記4つの中から協議離婚を選んだのですが、ほとんど私が用意した条件を相手がのむといった形で進めました。
弁護士さんに相談に行った話
手続きのことを何も知らなかったので、弁護士さんに相談に行くことにしました。
この時、そのまま問い合わせしても良かったのですが、相談料はいくら取られるのか分からないし、そもそも知り合いの弁護士さんも居ないし教えてくれる人もいなかったので、市役所の無料相談日に合わせて行くことにしました。
無料相談なので時間が限られています。この時は私は何も準備をしておらず、離婚準備の進め方だけを教えてもらったのみとなってしまいました。
無料とはいうものの、納得できる相談ができなかったので、今度は法テラスの無料相談に行くことにしました。
この時は養育費や慰謝料はどれくらいが相場なのかを聞きに行く目的があったので、相談はスムーズに終わりました。
離婚協議書の作成
慰謝料、養育費を取りたいこと、親権者のことをきちんと明記するために、離婚協議書を作ることにしました。
この協議書を作成することで、もし慰謝料等の支払いが滞ったとき、相手に請求できるようにしました。
この協議の内容を作成し、公証役場に持っていきます。公証役場で、きちんとした公正証書を作成してもらい、その後相手と二人で申し合わせ、印鑑を押しそれぞれ保管という形をとっています。
ここまでで相手と会った回数は2回、手続きにかけたお金は1万円もかけていなかった記憶があります。
私の離婚手続きはスムーズに行った方だと思います。双方の意見が合わなかったり、対立したときなどはもっと時間がかかるだろうし、かかるお金も変わってきただろうと思います。
離婚の時に覚えておきたい支援制度6選

ここからは離婚してから子どもの親権者となった時などに受けられる支援をまとめていきたいと思います。
児童扶養手当
この手当は18歳未満(一定の障害にある場合は20歳未満)の子どもを扶養しているひとり親家庭が受給対象となります。
収入制限がありますが、児童の養育のために支給しているもの。子どもの福祉の増進を図る制度です。
申込先は自分の住んでいる市町村の窓口となります。


児童手当
中学3年生の3月までの子どもを養育している時に支給される手当です。こちらも所得などの条件に応じて支給されます。ひとり親家庭でなくても、離婚協議中であってももらえる手当となっています。
児童育成手当、遺児福祉手当
都道府県や市町村によって異なる手当もあります。こちらはお住まいの市町村に問い合わせてみましょう。
ひとり親家庭の医療費助成制度
18歳未満(一定の障害にある場合は20歳未満)の子どもを扶養しているひとり親家庭で、医療保険に加入している家庭が受給対象です。
医療費の一部を補助してくれます。

母子・寡婦福祉資金の貸付
こちらは手当ではなく、一時的に資金を貸してくれる制度です。無利子、または少ない利子で貸付できます。
生活保護
生活に困っている人に対する救済制度です。最後の砦ですね。
生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、正業扶助、葬祭扶助
の8つの種類があり、必要に応じて受けることができます。
生活保護は、本人が生活扶助のために努力することが前提です。
他の制度の利用が優先だったり、働ける状態であること、援助できる身内がいることなどの努力を行っていても生活維持できないときの手当となります。
以上の手当や制度は、申請しないと受けられないものとなっています。
また、その期間が決められているものもあるので、忘れないようにしたいものです。
こちらにもそのほかの支援制度をまとめています。

まとめ
私の行った離婚手続きや準備などを紹介、また受けられる支援制度を紹介していきました。
これらを知っておいて、少しでも後悔しない離婚手続きを取ってもらいたいと願っています。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。